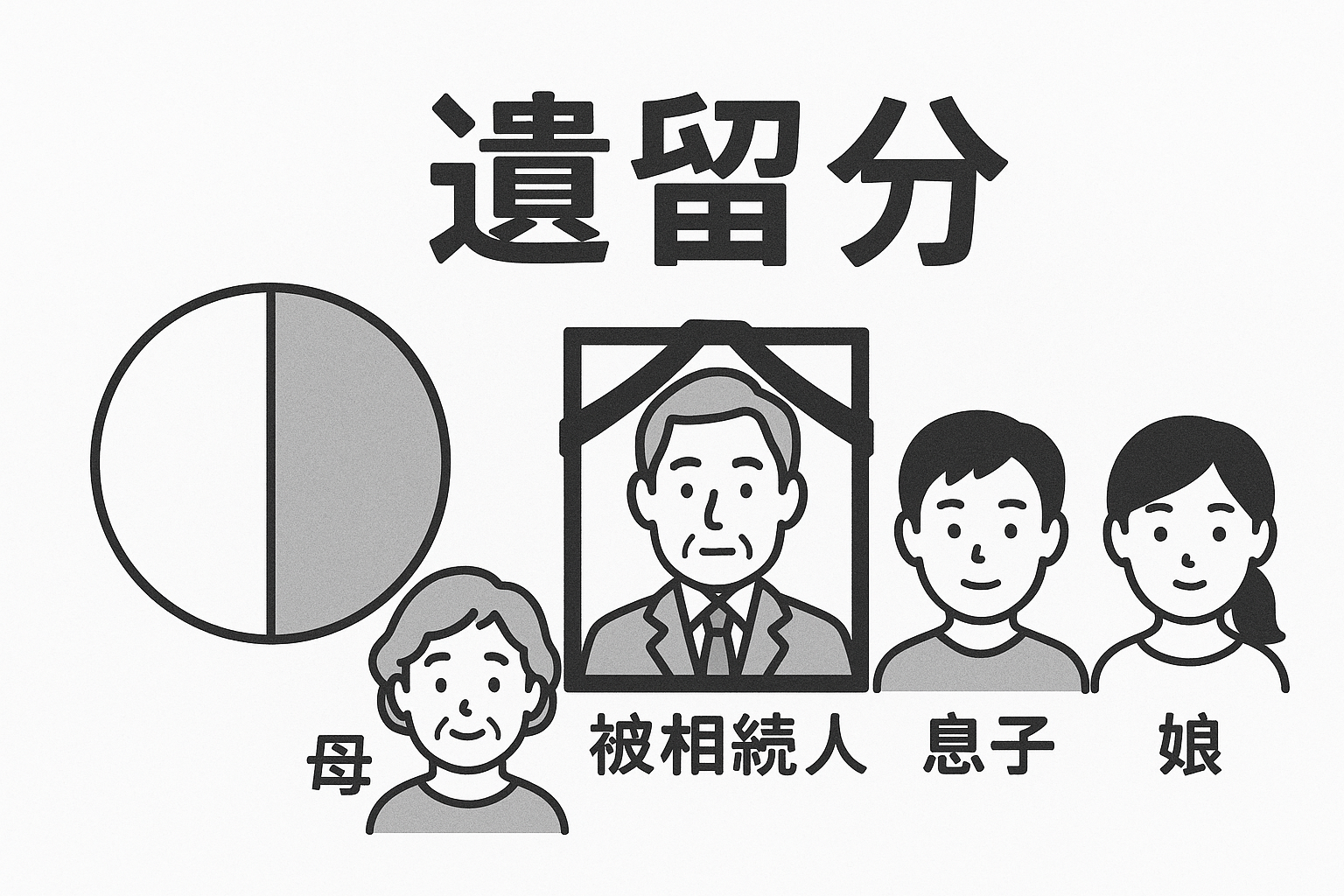遺留分と相続人全員の合意の関係 🤝
基本的な考え方: 相続人全員の合意があれば遺言と異なる分割ができますが、遺留分権利者が自分の遺留分を放棄することに合意していることが前提となります。
具体的なケース 📋
ケース1:遺留分を侵害する遺言がある場合
ケース2:全員合意で遺留分以下の分割をする場合
重要なポイント ⚠️
1. 遺留分の放棄は任意
2. 強制はできない
3. 後からの遺留分減殺請求
実務上の注意点 📝
書面での明記が重要: 遺産分割協議書には以下を明記することが推奨されます:
例文: 「相続人○○は、本件遺産分割により自己の遺留分を下回る相続分となることを承諾し、遺留分減殺請求権を放棄する。」
まとめ 🎯
相続人全員の合意による遺言と異なる分割は可能ですが、遺留分権利者がいる場合は、その人が自分の遺留分を実質的に放棄することに合意していることが重要な要件となります。
トラブル防止のためにも、遺留分に関する合意内容は書面で明確にしておくことをお勧めします! |